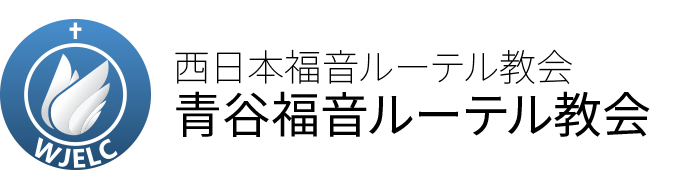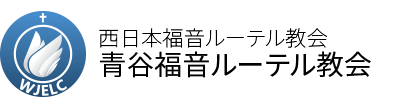「外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出て来るものが、人を汚すのである。」 マルコ7章15節
イエス様とファリサイ派の人々との「手を洗うこと」に端を発した議論です。
生活の中で信仰を生かしていくのか、生活と信仰とを分離するのか
イエス様とファリサイ派の人々との議論、それは第一に、生活の中で信仰を生かしていくのか、生活と信仰とを分離するのか、という議論でした。ユダヤ人たちが、きよめということをたいせつにして行った、それは、神を神として崇め、たいせつにするための掟でした。それはそれとして尊いことでしたが、そのことを通して、ユダヤ人たちは、世俗の世界を切り捨ててしまいました。それに対して、イエス様は、掟をたいせつにしながら、世俗の人々にも手をさし伸べて行かれました。
ほんとうの美しさとは
第二に、それは、ほんとうの美しさとは何かという議論でした。ファリサイ派の人々、彼らは、美しく生きようとしていました。でも、それは、人の前に美しくあろうとしているということを表していました。それに対して、イエス様は、ほんとうの人間の美しさ、それは別のところにあるとお教えになりました(7章15節)。イエス様は、外側ではなく、わたしたちの内にある罪が解決されなければ、ほんとうの美しさを身につけることはできない、とお教えになりました。
「かたち」か「いのち」か
第三にそれは、「かたち」か「いのち」か、という議論でした。ユダヤ人たちが、きよめということをたいせつにして行きました。でも、その手段である掟が目的となってしまっている、それが問題でした。「かたち」というものはたいせつです。でも、それがすべてになってしまうとき、「いのち」が失われてしまうのです。
イエス様は、生活と信仰とを分離するのでなく、生活の中で信仰を生かしていくようにとわたしたちを招いて下さるお方です。また、外側を取り繕うのでなく、内側から美しい者、きよい者として下さいます。そのように生きるためのいのちを与えて下さるお方です。そして、そのために十字架に死に、復活して下さったお方なのです。
(前川隆一牧師)