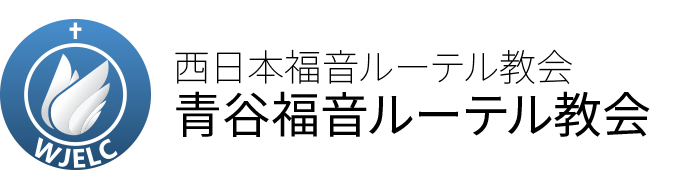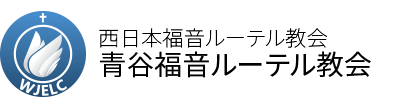「だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返ったのだ。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。」 ルカ15章32節
放蕩息子のたとえ話です。
違いと共通点
弟息子は、不真面目であり、自由であり、放縦でさえあります。兄息子は、それに対して、まじめであり、勤勉であり、従順です。そのような違いとともに、やはり血を分けた兄弟として、二人は、同じ根をもっているということができます。兄息子は、なだめに来た父親に、「このとおり、わたしは何年もお父さんに仕えています」と言いました。この「仕えています」ということばは、「奴隷として仕える」という意味のことばが使われています。兄息子は、愛と信頼からではなく、奴隷のように仕えていたということです。そして、弟息子は、そのような兄の思いを見抜いていたのでした。自分もお兄さんのように、奴隷のように仕えたとしても、取り分はたかが知れている。それならば、自分は自由に生きる。そう思って、彼は、父のもとを飛び出して行ったのでした。
非常識な行動
弟息子が帰っていたその場面、それは、この父親にとって、弟息子に向かって一言あってもおかしくない場面でした。また、ほんとうに回心しているのか、しばらく様子を見てもよい場面でした。けれども、父親は、それらのことを飛び越えて、弟息子をわが息子として迎え入れたのでした。どうしてか。逆に言えば、それは、このような父親の非常識とも思える行動がなかったなら、弟息子は、父親の息子として回復することはできなかったからでした(第一コリント1章18節)。
また、兄息子が怒って家に入らなかったように、ファリサイ派の人々、律法学者、イエス様の当時の宗教的指導者たちは、イエス様が徴税人、罪人たちを迎え入れて、彼らと食事をしておられる、彼らと親しくしておられるということに妬みを燃やして行きました。そして、その妬みが、最終的にイエス様を十字架へと追いやって行ったのでした。けれども、この十字架の愛によって、わたしたちは、自分を義とする罪から解き放たれることができるのです(ガラテヤ3章13節)。
(前川隆一牧師)