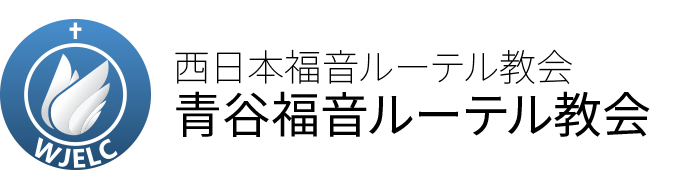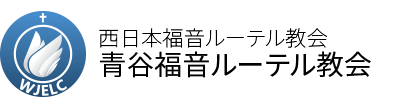信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。
ヤコブ2章17節
「人を分け隔てしてはならない」、「行いを欠く信仰は死んだもの」との表題のつけられている部分です。
人を分け隔てしてはならない
1節で、ヤコブは、「栄光に満ちた、主イエス・キリスト」と言っています。そのような「栄光に満ちた、主イエス・キリスト」を主としているのだから、ということと、その後に何が書いてあるかというと、それは、「人を分け隔てしてはなりません」ということです。別の訳では、「えこひいきしてはいけません」となっています。すばらしい神様の栄光の世界をわたしたちの前に示しながら、それを一気にわたしたちの身近な問題に結び付けているということです。
行いを欠く信仰は死んだもの
そして、後半の箇所である14節からは、行いを欠く信仰は死んだものであるということが記されています。ヤコブは決して、神様に信頼するということを否定して、行いとか実践がだいじであると言っているわけではありませんでした。そのような信仰ということを前提としながら、行いということ、実践ということを強調しているということです。
信仰と行い
信仰と行い、それは、言わば、車の両輪です。では、どのようにして、バランスの取れた信仰と行い、信仰と実践の生活に歩むことができるのでしょうか。聖書全体から言えば、信仰だけでもいけない、行いだけでもいけない、それら全体に神様の愛があって、はじめてほんものなのだと教えられています(Ⅰコリント13章)。そこで、先のことに戻って、ヤコブが「栄光に満ちた、主イエス・キリスト」を主としているのだから、伝道しなさい、とは言わないで、どうして、「人を分け隔てしてはなりません」と言ったのか。それは、教会は、まず、神の愛を土台としていなければならないということです。逆に、教会の中に神の愛があるとき、それが、そのまま、教会の伝道力となって行くということです。
(前川隆一牧師)