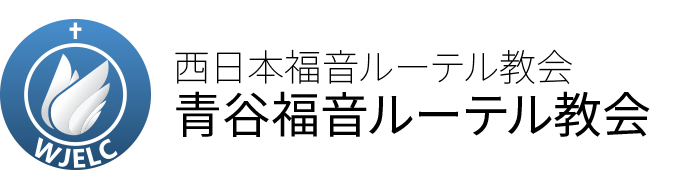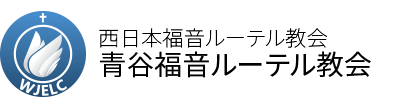また、イザヤはこう言っています。「エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる。異邦人は彼に望みをかける。」 ローマ15章12節
12章から始まった実践的な部分の締めくくりの箇所です。
忍耐の神
今日のところで、一つの特徴的なことと、それは、「~ように」という結びになっている表現が、二回出て来るということです(6、13)。結びが、祈りで結ばれているいわゆる牧会的対話と言われる表現です。そのような牧会的会話ということとともに、パウロが、神様をどのようなお方として信じ、祈って行ったのかということがとても重要です。パウロが、神様をどのようなお方として信じ、祈って行ったのか、その第一は、忍耐の神様ということです(5)。
希望の神
第二に、それは、希望の神様ということです(13)。パウロは、自分の最期ということ、死ということを意識しながら、このローマ信徒への手紙を書きました。けれども、パウロは、いつ死ぬか分からないからどうでもよい、というような刹那的な思いでいたわけではありませんでした。パウロは、当時の理解からすれば地の果てであるスペインにまで行って、福音を伝えたいと願っていました。
真実の神
第三に、それは、「真実の神」ということでした(8~9)。パウロの抱えていた大きな悩みは、なにか。それは、人間関係の悩みでした。それは、信仰の強い人が、信仰の弱い人を受け入れることができないという悩みでした。また、それは、ユダヤ人クリスチャンが、異邦人クリスチャンを受け入れることができないという悩みでした。そのような悩みを持ちながら、パウロは真実の神を見上げて行きました。人間が、真実を貫くとき、それは、しばしば裁きになります。けれども、神の真実、それは、わたしたちの不真実を真実に変える憐れみとなるのです。それは、そのために、イエス様が十字架で血を流されたからです。そして、主の十字架、それは、ユダヤ人と異邦人の間の仲たがいも取り除き、一つとするものである。そうパウロは、ここで言っているということです(12節)。
(前川隆一牧師)