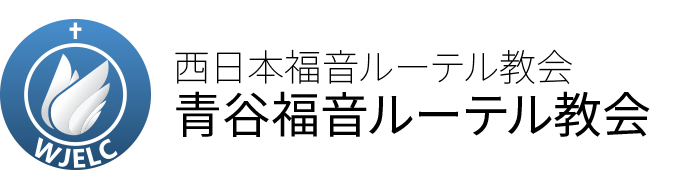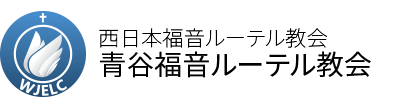マタイ5:1~6
【心(霊)の貧しい人々】 ルターは自分のことを「まことに我らは神の乞食なのである」と書き記した。人間は自分を中心とした価値観や人間通しの相対的な比較の中で「富んでいる」と思っている。しかし、絶対的な創造主なる神様の前では何も誇るものがなく、何の価値もない「霊が貧しい」者であることを知らされる。しかし、その私を愛しその罪の身代わりとして主イエスが十字架で死なれたゆえに信じる者は「神の国」に生きることができる。これが「幸いである。」【悲しむ人々】 主イエスはこの世における人間の悲しみを体験された。悲しみの中でもがく私たちに寄り添い、慰めて下さる。「慰められる」とは「悲しみ」の根源である罪を十字架で解決し、喜びに変えられることなので「幸いである。」
【柔和な人々】 「柔和」とは優しさや謙遜ではなく、「耐えること、肘を張らないで生きること。」「地を受け継ぐ」とは人間本来の生き方ができるようになるので「幸いである。」
【義に飢え渇く人々】 「義」とは「律法の正義」ではなく、神様から与えられる福音としての「神の義」。ルターがこの「神の義」を飢え渇き求めてみ言葉から再発見したことが500年前の宗教改革となった。み言葉を律法としてではなく福音として受け取る者は、神様の愛と恵みで満たされるので「幸いである。」
(深尾吉照牧師(大田・仁摩福音ルーテル教会))