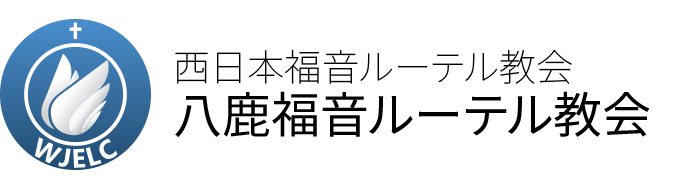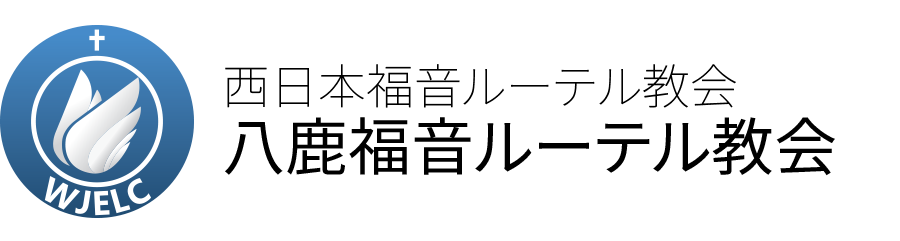2025年10月26日(日)
=あなたがキリストの上に立ち続けるために=
【説教要旨】<福音書>ルカの福音書18章9~14節
イエス様は「自分は正しいと確信していている人たち」に話しておられます。それを聞いて私たちが思い出すのは、パリサイ人/律法学者たちです。
ですからイエス様は、思い上がっている人々をも、救いに導くためにこのたとえ話をされたのです。
ここでイエス様は<祈りの本質と人の心の姿勢>について語っておられます。 祈りは、神との交わりです。祈りには三つの目的があります。
第一は、神との関係を深めることです。祈りによって、人は心から神に近づくのです。
第二は、自己認識と悔い改めです。祈りを通して、人は神の前で自分の罪や弱さを認めて悔いるのです。
第三は、神の憐れみにすがることです。祈ることによって、神の義に頼る姿勢を教えられるのです。
さて話の中のパリサイ人は、祈りの中で、他の人々の悪い点を列挙して「自分はそのような者でないこと」を感謝しています。また特に取税人のようでないことを感謝しています。そして最後に自分を誇っています。それは祈りのことばでしょうか。
祈りは神との個人的な交わりの場です。自分を他の人と比較する場ではありません。人の悪口を言う場ではありません。自分を誇る場でもありません。ですからパリサイ人は、祈る者としての基本的な<祈りの立ち位置>が誤っています。
さて、取税人も宮に来て祈りました。取税人は、パリサイ人や律法学者たちとは社会の対極にいる人たちです。取税人は、宮の中心から遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言います。
「神様、罪人の私を憐れんでください」。取税人は「人から罪人扱いされてもいい」と思っていた。でも誰かから、永遠のいのちに生きるすばらしさを教えられ、それで罪を悔い改めて祈るために宮に来た。
取税人は「神様、罪人の私をあわれんでください」と祈りました。「あわれんでください」との祈りのことばは、罪が赦されることを願うだけではなく、罪によって遮断された神との交わりの回復を願う祈りのことばです。
何故、パリサイ人の祈りと取税人の祈りがこれほど違ったのでしょうか。
たとえ話の中で、パリサイ人は立って祈っています。どこに立っていたのでしょうか。ここでは、神の前での“心の在り方”が問われています。パリサイ人は、自信に満ちた自己中心的な立ち方をしていました。
パリサイ人は、自分の正しさを誇示する位置に立っていたのです。パリサイ人は、自分の義の上に立って、周囲を見下ろす姿勢で神に向かって祈ったのです。
そのようなパリサイ人の立ち方は、神との距離が近いようで、実は心は神から遠く離れていました。
それに対して取税人の「遠く離れて立つ」姿は、神のあわれみにすがる心を象徴しています。取税人は、罪の悔い改めと神との交わりを回復したいとの思いの上に立っていたのです。
取税人は遠く離れて立っていましたが、彼の心はパリサイ人よりもずっと神の近くにあったのです。
それで主は、私たちに問われます。「あなたの立ち位置はどこですか」と。私たちは罪を悔い改めて、イエスを救い主と信じたクリスチャンです。ですから神との交わりを回復した者です。
しかし私たちは、いかにた易く罪に陥ることでしょうか。主が私たちに求めておられるのは、取税人のように胸をたたいて、主の前に自分を見つめ直すことです。
そのようにして自分を見つめ直すとき、そこに見えてくるのは“罪人としての自分の姿”であり、またそのような惨めな者を憐れんでくださった十字架上のイエス・キリストの姿です。
ですから、私たちの信仰者としての立つべき場所は、イエス・キリスト以外にありません。
「イエス・キリストの上に立つ」。それは、あなたが常に罪を悔い改め、十字架のイエス・キリストを見続けることです。
そのような者を、主は“義なる者”と見なしてくださり、ご自分に近くある者として高めてくださるのです。主は言われます、14節『だれでも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです』と。