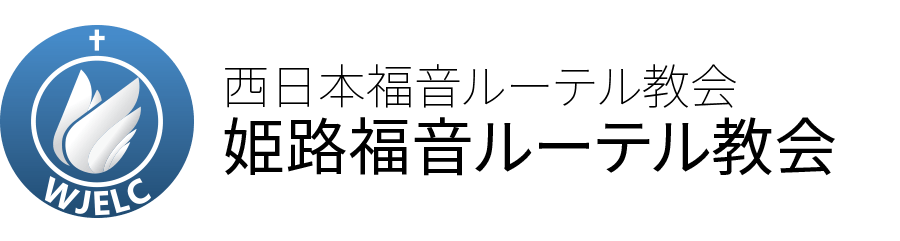マルコの福音書10章46-52節
きょうは宗教改革主日です。1517年10月31日、マルチンルターが、当時教会が販売していた贖宥状(いわゆる免罪符)を非難するために「95箇条の提題」という文書を教会前の掲示板に貼り出したことが、宗教改革のきっかけと言われています。贖宥状というのは「この札を買えば天国に行ける」という札です。しかしルターは「天国に行くために何かを買う必要も、良い行いをする必要もない。神の御子イエスキリストがすべての人間の罪を背負って身代わりに十字架で死んでくださったので、このお方を救い主として信じるだけで天国に行ける。これが聖書の教えだ。」ということを主張したのでした。
エルサレムに近いエリコという村にイエス様たちが来られた時、バルテマイという目の見えない人が「ダビデの子のイエスさま。私をあわれんでください」と叫びました。「ダビデの子」というのは「キリスト」を指す言葉です。しかし多くの人は「キリストというのはかつてのダビデ王のように、武力によって国々を制圧し、イスラエルを再び偉大な国にしてくれる存在」という意味で「キリスト=ダビデの子」と呼んでいたのです。しかしバルテマイは、ダビデが王であると同時に「祭司」でもあったことを知っていました。祭司は人々の罪のゆるしを神様に願う役目です。イエス様も同じように、「王であると共に祭司である」ということをバルテマイは信じ、大胆にイエス様にあわれみを求めました。「それがゆるされる」と信じていたからです。イエス様もその信仰を喜ばれ、彼を呼んでその目を開かれました。それはただ肉眼を開いただけでなく、「わたしの弟子となってついて来なさい」ということでもありました。バルテマイもそれに応え、イエス様の弟子としてついて行きました。
イエス様の弟子は、神様の子どもですから、お祈り1つで世界を変えられる、ある意味王のような存在です。しかし、だからこそ、人々の上に君臨するのではなく、祭司のように人々に仕えるべきなのです。聖書に「あなたがたは…王である祭司」(Ⅰペテロ2:9)とある通りです。
「キリスト者は、全てのものの上に立つ自由な君主であって、何人にも従属しない」「キリスト者は、全てのものに奉仕する僕であって、何人にも従属する」(マルチン・ルター「キリスト者の自由」より)
(永田 令牧師)