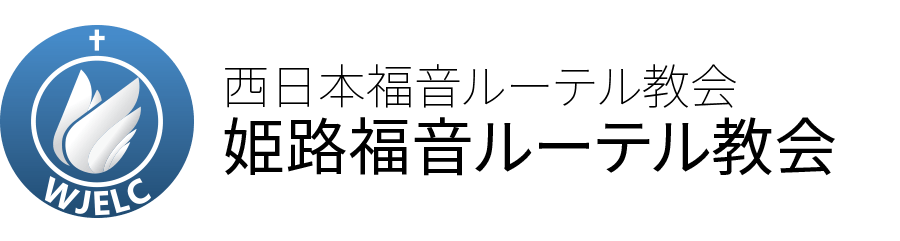2024/8/4礼拝メッセージ
ヨハネの福音書6章24-35節
8月の第一日曜日は「平和の主日」です。きょうのタイトル「けんかはよせ 腹がへるぞ」は、漫画家水木しげるさんの名言です。この言葉は水木さんの戦争体験から来ています。しかしあれから80年たつのに今もウクライナやガザで戦いがあり、多くの民間人が飢えている状態です。なぜでしょうか?人間というのはどうしても「相手を理解するより自分のことを理解してほしい」と思うものです。そして「自分の苦しみはあの人のせい」と考え、「けんかをよせ」と言われても「向こうに言ってくれ」となるのです。
イエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人以上の群衆を満腹にした後、群衆はイエス様をむりやり自分たちの「王」にしようとしました。「この人が王様になれば、もう飢えることはない」と思ったのです。しかしそんな自分勝手な方法で飢えを満たしても、すぐまたおなかがすきます。イエス様はおっしゃいました。「なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠のいのちに至る食物のために働きなさい」(27)。「なくなる食物」とは物質的な食物や財産などです。それらは必要なものですが、すぐになくなります。しかし魂が満たされたなら決して飢えることなく、永遠のいのちに至ります。では「魂を満たす」にはどうしたら良いのでしょうか?多くの人々は「良いことや正しいことを行うこと」と考えます。しかし必要なことはただ一つ。神様が世に遣わされた「イエスキリスト」を信じるだけです。イエス様は人間がなすべき行いをすべて成し遂げた末に、何も出来ないわたしたちの代わりに十字架で罰を受けて死んでくださいました。だからわたしたちは、何も良いことが出来なくても、悔い改めてイエス様を信じるだけで魂の満たし、永遠のいのちをいただくことが出来るのです。これが福音です。「福音は羽毛ほどの重さのものもわれわれに負わせることがない」(カール・ヴィスロフ)。イエス様を信じて洗礼を受け、聖餐にあずかる人は「イエス様を食べる」人であり、その人は永遠のいのちを持っています(54)。その人の中にはイエス様の霊である聖霊様が住んでおられますから、イエス様のように「けんかをやめる」人になっていきます。そしておなかも心もいっぱいになります。「なくなる食物」によってではなく「いつまでも保ち、永遠のいのちに至る食物」によって。
(永田 令牧師)
救い主との出会いは逃がせない
「救い主との出会いは逃がせない」 2024/9/8
マルコの福音書7章24-37節
イエスさまはツロの地方(今のレバノン共和国)に行かれました。すると、悪霊につかれた娘をもつ女性がやって来てイエスさまの足もとにひれ伏し、娘から悪霊を追い出してくださるよう願いました。ところがイエスさまは、「まず子どもたちに満腹させなければなりません。子どもたちのパンを取り上げて、小犬に投げてやるのは良くないことです」(27)と、なんと娘を小犬に、ユダヤ人を子どもにたとえて、女性の願いを断られたのです。イエスさまは民族で人を差別するのでしょうか?そうではありません。イエスさまがまだ十字架にかけられていないこの段階では、ユダヤ人ではない異邦人にまだ福音を語るわけにはいかなかったのです。イエスさまは十字架の上でユダヤ人、異邦人、双方の罪を引き受けて、双方の罪をゆるされました。十字架によって初めて両者を分ける隔てがなくなったのであって、それまではまだ隔てがあったのです。
イエスさまの言葉にツロの女性は答えました。「主よ。そのとおりです。でも、食卓の下の小犬でも、子どもたちのパンくずをいただきます」(28)。何という信仰でしょう。彼女は、自分が選ばれた人ではなく、救われる資格もないことを完全に認め、ただ神さまの憐みだけが希望のすべてだと言ったのです。神さまにすべてを委ねる信仰の表明です。これを聞いてイエスさまは「そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出ていきました」(29)とおっしゃいました。異邦人である彼女が神さまの主権を完全に認めたことで、異邦人とユダヤ人の隔てが必要なくなったのです。
このころのイエスさまは、ガリラヤの群衆、パリサイ人や律法学者たち、さらにイエスさまの弟子たちさえ、一向にイエスさまが救い主であることを悟らない状況に、疲れを覚えておられました。しかし今日のツロの女性の信仰に大いに励まされて、そのあとデカポリス地方へ向かい、耳が聞こえず口がきけない人の耳と口を開かれました。天を見上げ、苦しみの声を上げながら開かれました。それによってご自分が救い主であること、しかも人々の苦しみを共有し、人々とともに天に苦しみを訴える救い主であることを示されたのです。ツロの女性がそうであったように、わたしたちもイエスさまとの出会いを逃さずに、イエス様を「自分の」救い主として受け入れましょう。自分と同じ地平に立ってくださる救い主として。
(井上 靖紹 長老)