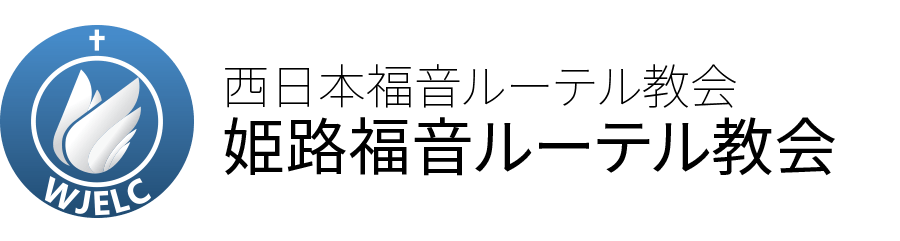ルカの福音書16章19~31節
イエス様のたとえ話「金持ちとラザロ」は、生前の立場が死後に逆転する物語です。紫の衣をまとって毎日贅沢に遊び暮らす金持ちと、その門前で飢え、全身おできに苦しむ貧しいラザロがいました。死後、金持ちは地獄(ハデス)で苦しみ、ラザロは天国(アブラハムのふところ)で憩うという大逆転が起こります。
この金持ちが地獄へ行ったのは、単に裕福だったからではありません。信仰の父アブラハム自身も非常に裕福でした。金持ちの罪は、あり余る富を持ちながら、目の前で苦しむラザロにあわれみを示さず、食べ物一つ与えなかったことにあります。この金持ちは、神様や聖書を知らない者ではなく、神様もアブラハムもモーセも預言書も知っていました。それにもかかわらず、モーセや預言者たちが命じた「貧しい者に手を差し伸べ、飢えた者にパンを分け与えよ」という神様の言葉を無視したのです。神様ご自身がしいたげられる者を助け、飢えた者にパンを与えるお方です。その神様を愛すると言うならば、自分もそのように生きるべきなのです。
イエス様はこの話を「金の好きなパリサイ人」に向けて語られました。「自分たちは神に愛されているから裕福なのだ」と信じ、「人は神と富の両方に仕えることは出来ない」と言われたイエス様をあざ笑った人たちです。彼らは自分の富の使い方について、それが本当に神様の御心にかなっているかどうか考えませんでした。地獄に落ちた金持ちは兄弟を心配する優しさを見せますが、その優しさを生前ラザロに向けることはなかったのです。
この物語は、救いが「アブラハムの子孫であるか否か=ユダヤ人であるか否か」とは無関係であることを示しています。天国へ行けるのは神様の御心を行う人、すなわち神様と隣人を愛する人だけです。しかし、パリサイ人に限らず、すべての人は罪のためにそれができません。ラザロが救われたのは、貧しかったからでも優しかったからでもなく、神の助けを信じる信仰があったからです。「ラザロ」という名が「神が助ける」という意味を持つことでそれがわかります。私たち人間は、日頃の行いによってではなく、私たちの罪を背負って死んでよみがえられた神の御子イエス様を信じる信仰によって「神に助けられ」るのです。イエス様を信じるとき聖霊様が与えられ、イエス様のように自分が犠牲を払っても隣人を助ける、そんな人に変えられていきます。「たとえ胸の傷が痛んでも」困った人を助けるアンパンマンのように。
(永田 令牧師)